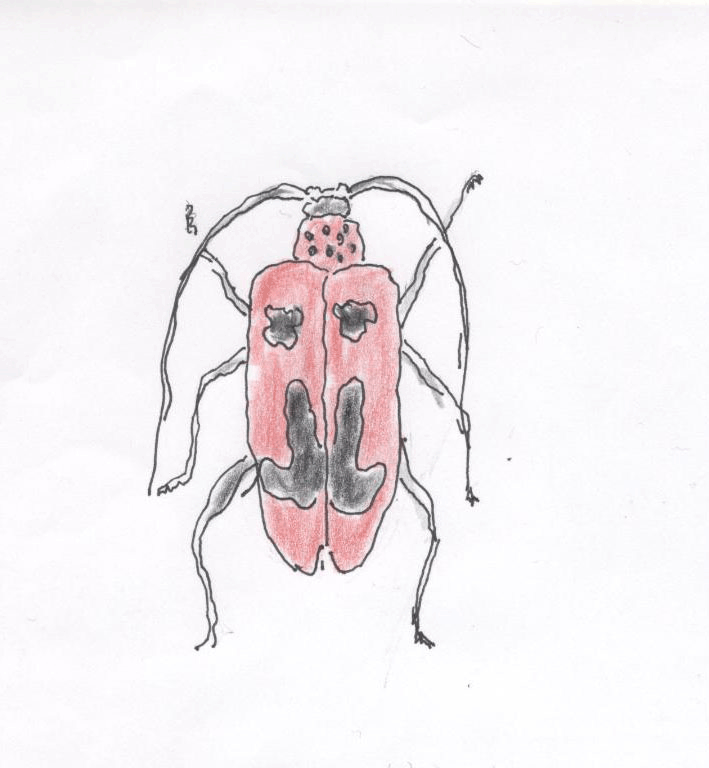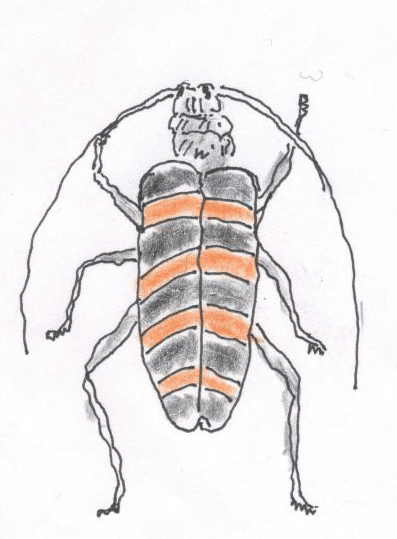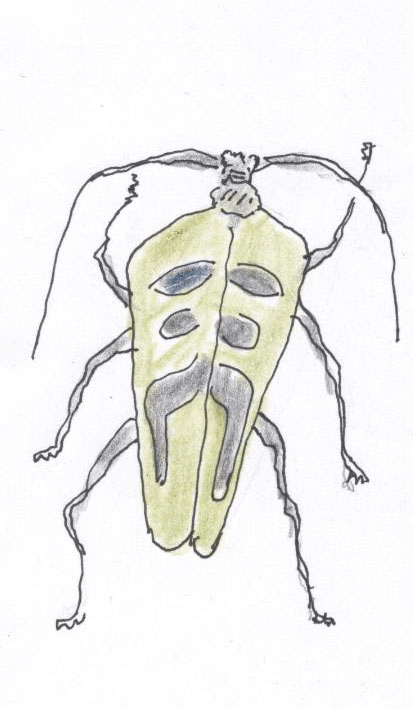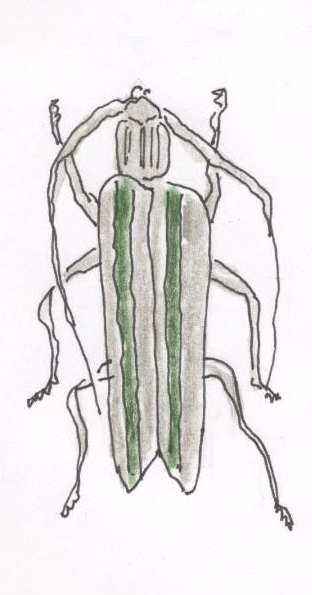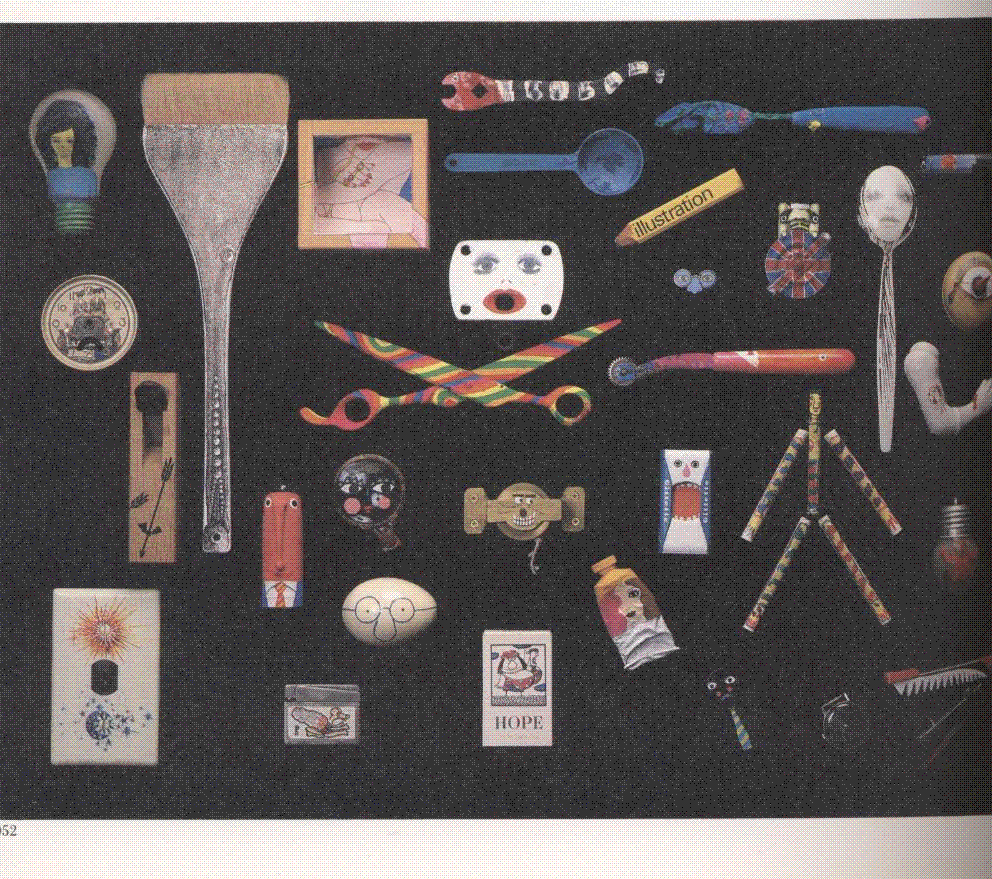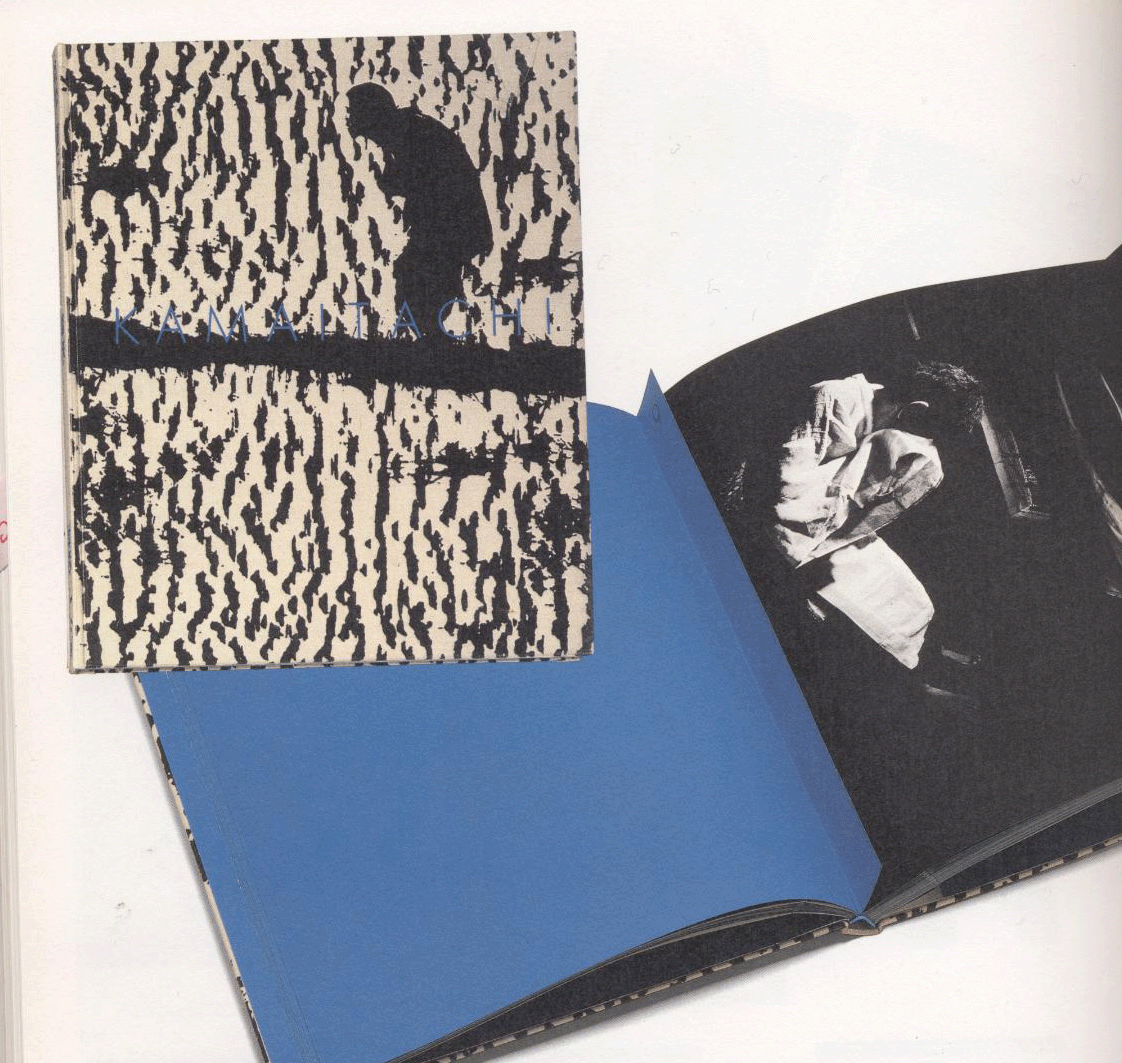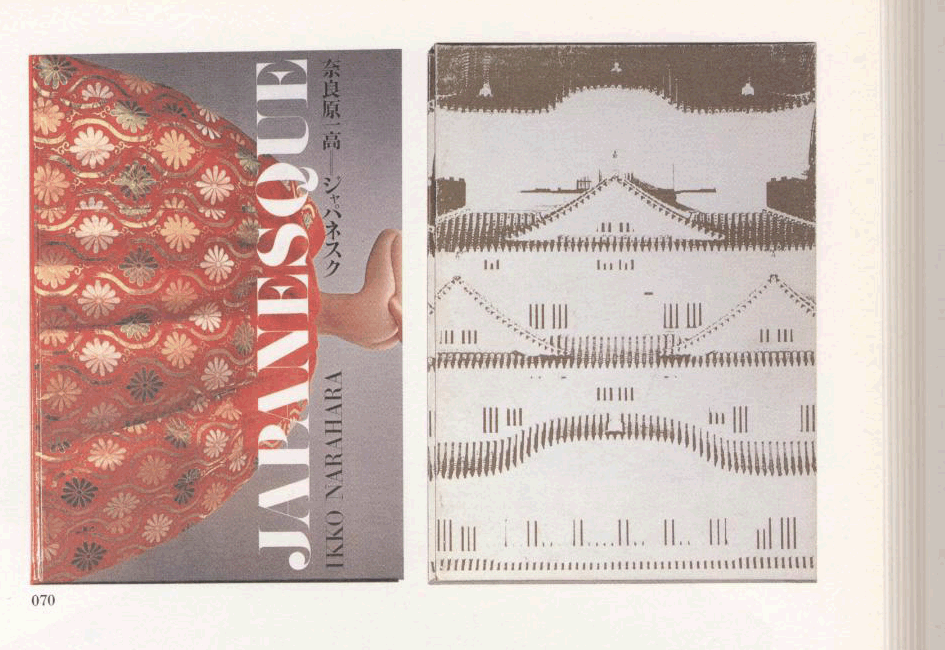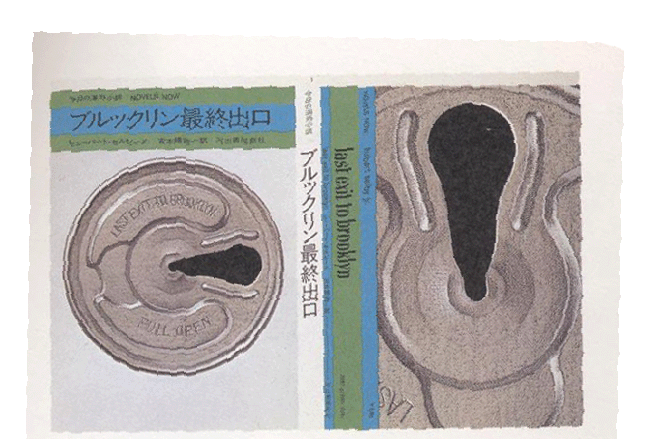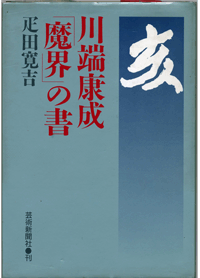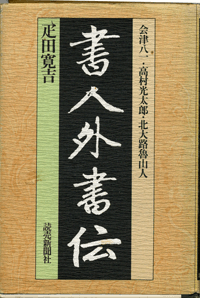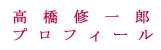
| 書歴 |
1986年 疋田寛吉 主催「我流毛筆の会」入会
1991年 第1回個展(京橋 京画廊)
1992年 「我流毛筆展」出展
1994年 「我流毛筆展」出展
1996年 「我流毛筆展」出展
1998年 疋田寛吉先生死去
2001年 第2回個展(パリ ESPCE JAPON)
2002年 第3回個展(西麻布 ブラックホール)
2006年 第一回 新「我流毛筆展」出展
2007年 第二回 新「我流毛筆展」出展
2008年 第三回 新「我流毛筆展」出展
我流の書をめざす私ですが、我流の書とは自分流の書ということになります。
それでは、書に於ける自分とは一体どんな自分なのでしょう。
中々難しい問いで、今だその自覚を持てることができません。
そこで私のプロフィールを印して私という人間の理解につなげてもらえればと考えました。
それでは私のプロフィールをどのような形で描くことが
私の理解につながるか?考えた末
私が今まで出会い、とても大きな影響を得た人々の事について語ることで
今の自分を見つめ、自分を語ってみようと思いつきました。
洋画家 青木正春
先生のアトリエに伺うようになったのは僕が6才ぐらい、確か1950年代の事でした。
当時、岡山の市街地でも戦後の復興は見られず、あちこちに焼跡の広場が点在し、
これといった建物も見かけない、着る物も食べる物も不自由な時代でした。
その頃青空幼稚園といって、お天気の良い日に限り、わずかに残骸を留めた小さな公園跡で
アコーデオンを持った先生が子供達を集め歌や踊り、紙芝居などで遊んでくれていました。
今でも何にも無い時代の、あの妙に澄んだ空虚な青空が今でもくっきりと心に残っています。
街にも自分を取りまく家の中にも色彩が乏しく、色に飢えていた僕にとって
先生のアトリエは子供心にも、それは強烈な印象を抱かせる場所でした。
油絵の具のうっとりするような美しい色、色、色・・・。異国を思わせる油の香り、
それまで見たことも無いモダンな絵。
先生が採集した蝶や甲虫の標本は、自然の造形とも言える色彩と形の素晴らしい作品
となって僕らの眼を奪い、大きな鳥小屋で飼育される野生の小鳥達の可憐な姿は
僕らをうっとりとさせたものでした。
それらから受ける様々な刺激は幼い心にも、現実を忘れさせるエキゾチックな、そして
経験した事の無い好奇心に満ちた気分を抱かせるのでした。
今にして思うと、それは子供なりに戦後特有の「自由な気分」を
満喫していたのだと思います。何にも無い貧しい時代であったからこそ、大きな憧れと夢を
抱く事が出来た。それを育む楽園とでも言うべき先生のアトリエに出逢った事は
僕の人生にとって、大きな大きな幸運であったと思います。